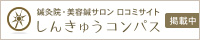鍼灸コラム
芦屋の女性鍼灸師が解説|不安と自律神経、めまい・耳鳴り・痛みの関係

不安が強いと、めまい・耳鳴り・動悸・不眠など自律神経の不調が起こりやすくなります。芦屋の女性鍼灸師が、不安と身体の関係、メンタルケアに鍼灸が向いている理由を解説します。
不安が強いとき、身体はどんなサインを出している?
「めまいや耳鳴りが続くと、検査では異常がないのに重い病気ではないかと不安になる」
「不安が強くなると、腰が痛くなったり、頭が痛くなったり、全身がしんどくなる」
「症状をネットで調べるほど怖くなり、動悸がして眠れなくなる」
芦屋で鍼灸院をしていると、
めまい・耳鳴り・自律神経の乱れ・メンタルの不調 に悩む女性の方がとても多いと感じます。
不安は「気持ちの問題」と思われがちですが、
実際には 自律神経・内臓・筋肉の緊張と深く関係する【身体の状態】 です。
この記事では、
不安が強いと起こりやすい体調不良や病気、
そして 鍼灸がどのようにメンタルケアや自律神経調整に役立つのか を、
芦屋の女性鍼灸師の臨床視点からお伝えします。
不安が強い状態とは「自律神経が休めていない状態」
不安が強いとき、身体は常に
交感神経が優位(緊急モード) になっています。
この状態が長く続くと、
副交感神経に切り替わるタイミングを失い、
身体は「休む・回復する」ことができなくなります。
その結果、さまざまな不調が現れます。
不安が強い人に多い自律神経の症状
・めまい、ふらつき
・耳鳴り、難聴
・動悸、息苦しさ
・胃腸の不調(胃痛、食欲不振、下痢)
・不眠、寝つきが悪い
・頻尿
・首、肩、背中の強いこわばり
・原因のはっきりしない痛み
・倦怠感、疲れが取れない
これらは病院の検査では異常が見つからないことも多く、
「ストレスですね」「様子を見ましょう」と言われてしまうケースも少なくありません。
しかし、身体は確実にサインを出しています。
東洋医学から見た「不安」と自律神経の関係
東洋医学では、不安や緊張は心だけでなく、
肝・脾・腎 といった内臓の働きと深く関係すると考えます。
不安が強い方に多い状態は、
・緊張が抜けず「気」が滞っている状態
・自律神経の乱れにより胃腸の働きが低下している状態
・考えすぎによるエネルギー消耗で回復力が落ちている状態
これは性格や気の持ちようではなく、
身体のバランスが崩れている状態 です。
なぜ鍼灸はメンタルケア・自律神経調整に向いているのか
鍼灸は、
「前向きになりましょう」「頑張りましょう」というケアではありません。
・自律神経の切り替えをサポートする
・無意識に入っている筋肉の緊張をゆるめる
・内臓の働きと血流を整える
・身体に安心できる感覚を取り戻させる
言葉で不安を抑えようとするのではなく、
身体から先に落ち着かせることで、心が自然に整っていく。
それが鍼灸によるメンタルケアです。
不安が強い人ほど、実は鍼灸が合いやすい理由
芦屋で女性鍼灸師として施術をしていると、
不安が強い方ほど次のような傾向があります。
・真面目で責任感が強い
・頑張りすぎてしまう
・周りに気を遣い、自分を後回しにする
・美容や健康への意識が高い
美容鍼で来院された方の中にも、
めまい・耳鳴り・自律神経の乱れが、
シミ・シワ・たるみなどの見た目のお悩みの根本原因だった、
というケースは少なくありません。
「心を変えなくていい」という鍼灸という選択
不安があるからダメなのではありません。
不安は、身体が「休みたい」と伝えているサイン です。
芦屋で女性鍼灸師として施術を行う中で実感しているのは、
身体から整えることで、心は自然に落ち着いていく ということ。
・自律神経の乱れ
・めまい、耳鳴り、難聴
・原因のわからない痛み
・メンタルの不調
病院で解決しない症状に悩んでいる方にとって、
鍼灸はやさしく、現実的な選択肢の一つです。
病院で異常がないと言われ、不安を感じている方へ
・不安は「気持ち」だけの問題ではない
・自律神経と身体の状態は深くつながっている
・めまい、耳鳴り、難聴、痛みは身体からのサイン
・鍼灸は心ではなく、身体から整えるケア
・頑張らなくても、整う道はある
ヒプノセラピーの誤解

「操られる」ではなく【自分に戻る技法】
それがヒプノセラピーです
芦屋・神戸・西宮など阪神間でヒプノセラピーについてのご相談を受ける中で、今もなお多くの【誤解】があると感じています。
ここでは、よくいただく質問をもとに、ヒプノセラピーの本質をお伝えします。
✖ 誤解①「催眠術みたいに操られる」
まず、最初にお伝えしたいのは、ヒプノセラピーは 催眠術とはまったく別物だということです。
セッション中はしっかり意識があります。
・声が出せる
・イヤなことはすぐに「NO」と言える
・思考はクリアなまま
つまり、操られるとは無縁です。
ヒプノセラピーとは、本来 【自分の中心に静かに戻るための心理的プロセス】で、誰かにコントロールされるものではありません。
✖ 誤解②「暗示で強制的に変えられる」
これもよくある誤解です。
ヒプノセラピーの変化は、強い暗示や操作によって起こるのではありません。
むしろ、
・こころの緊張がゆるむ
・内側の声が届く
・本当の望みが見える
といった自然な【内側の動き】が変化を生みます。
外側から行動を矯正するのではなく、あなた自身の【意味づけ】が優しく変わっていくのが特徴です。
✖ 誤解③「記憶を消したり操作される」
記憶そのものは変わりません。
ただし、その【記憶の捉え方(解釈)】が変わることで全く違う意味を持ち始めることがあります。
例えば
「人と一緒だと疲れるのは精神が弱いから」と思っていた過去が、
「感受性が高いから人に寄り添うことができていた」
という 新しい物語 に変わることがあります。
これがヒプノセラピーで起こる【再翻訳(リフレーミング)】
トラウマケア・潜在意識の整理・自律神経の安定にもつながります。
✖ 誤解④「前世に飛ばされる」
これはSNSなどの影響での間違った解釈です。
ヒプノセラピーは勝手に前世へ連れていかれるようなものではありません。
そもそも前世があるかどうかは誰にもわかりません。
より、深い潜在意識の中で、現実では説明のつかない感覚になることがあります。
ただし、セッション中の意識はしっかり保たれているため、あなたの望まないイメージであれば避けることができます。
もちろん、前世のイメージとして出る場合もあります。
例えば
・着ている服が明らかに現代のものと異なる
・中世のヨーロッパや江戸時代のような場所にいる
・家族や友人ではない、知らない人がたくさんいる
など
でもそれは、潜在意識が物語として、今の悩みを整理しやすい表現として象徴的に見せてるのかもしれません。
つまり、前世そのものが目的ではないということ。
重要なのは、そこから浮かび上がる【感情】【気づき】【癒し】がテーマ。
あなたが今、必要としている情報を「比喩」として受けとっているに過ぎないので怖がる必要はまったくありません。
ヒプノセラピーとは ― 内側の声を取り戻すプロセス
ヒプノセラピーとは、外から修正するのではなく、本来の自分に戻るための【心の回復プロセス】です。
静かで、あたたかく、安心できる時間。
決して怖いものではありません。
茜メソッド心
ストーリー・コクリエーション・ヒプノセラピーについて
ASHIYA茜senでは、初めての方には東洋医学の「心身一如」の視点を重ねながら独自の 《ストーリー・コクリエーション・ヒプノセラピー》 を取り入れています。
これは、
- 抑えてきた感情
- 本当は望んでいたこと
- 大切にしたかった価値観
を丁寧に拾い直し、【人生の物語を編み直す】 心のケア です。
外側を変えるのではなく、あなたと一緒に 内側の物語を共創(コクリエーション)していく セッション。
これが茜メソッド心の核となります。
こんな方に向いています
- 感じやすくて疲れやすい方
- 生きづらさを抱えている方
- 自分責めが止まらない方
- 人間関係でいつも同じパターンを繰り返す方
- 東洋医学的な【心身のつながり】に興味がある方
心がゆるんだ瞬間、身体も静かに整い始めます。
さいごに
ヒプノセラピーは
【操られるもの】でも
【記憶を操作するもの】でも
【前世に飛ばすもの】でもなく、
あなた自身の物語を取り戻す技法です。
本来、あなたが歩むべきラインを進んでいると心身に多少トラブルがあっても自分の力で解決できます。
心と身体、自律神経、潜在意識。
そのすべてが整い始め、本来の力を取り戻し【静かな回復】を、必要な方に届けられたらと思っています。
進化系人間のあなたへ(感じすぎるのは世界の変化に先行してる)

HSP・感受性が高い・敏感すぎて生きづらい人へ
それは進化のサインです
最近、当院のもとを訪れる人たち(芦屋・神戸・西宮エリア)に共通するのは「能力が高すぎて生きづらさを感じている」ということです。
これはHSP(Highly Sensitive Person)やエンパス気質の方に多く見られます。
本人はそのことに気づかず、「周囲に合わせられない」「できない自分が情けない」と自分を責め、疲れ果ててしまいます。
けれど、それは【できない】のではなく、【感じすぎるほど進化している】のかもしれません。
社会の仕組みが、まだその感性の速度に追いついていないだけなのです。
進化系人間という存在
私はこうした方たちを「進化系人間」と呼んでいます。
彼らは、直感・感覚・共感力が非常に発達し、場の空気や人の感情、言葉にならない【気】の変化を敏感に感じ取ります。
いわば、神経の解像度が高く、世界のエネルギーを高精度にキャッチしている人たち。
その分、常に大量の情報や感情を受け取り続けるため、疲れやすくなり、「自分は弱い」「社会不適合だ」と誤解してしまうのです。
しかし、それは弱さではなく、感受性の進化なのです。
旧式社会とのずれ=生きづらいの正体
今の社会は「効率」「スピード」「結果」を基準に動いています。
でも、進化系の人たちはその直線的なリズムでは生きられません。
彼らの世界はもっと有機的で、波のようにゆるやか。直感で理解し、感情で動き、エネルギーで人とつながります。
そのため、旧式の社会の中では摩擦が生まれ、「不安」「疲労」「体の不調」として現れることがあります。
けれど、それは壊れているのではなく、社会の枠が古いだけ。
神経が未来型だからこそ、周波数が合っていないのです。
「合わない」は「間違い」ではない
感じすぎる、考えすぎる、共感しすぎる
それは欠点ではなく、未来を先取りした「高感度センサー」
ただ、その繊細な感性を守り、使いこなす方法をまだ知らないだけなのです。
感性を社会で生かす「翻訳」
感受性の高い人たちは、目に見えないエネルギーや気配、人の想いを感じ取る力を持っています。
けれど社会は、それを理解できる言語をまだ持っていません。
だからこそ必要なのが、「翻訳」して伝えること。
内側の感性のことばを、外の世界でも通じる言葉に変えるそれが翻訳の力です。
たとえば、
「人混みがつらい」は「刺激に敏感で神経が繊細」へ。
「気分の波が大きい」は「共感力が高く、周囲の影響を受けやすい」へ。
言葉を少し変えるだけで、「問題」は「個性」や「才能」へと姿を変えます。
東洋医学の視点
東洋医学は、「人と自然はひとつ」という思想の上に成り立っています。
身体と心、内と外、陰と陽、それらが互いに影響し合い、ひとつの「気」として循環していると考えます。
だから、感受性の高い人が社会で疲れやすいとき、
それを「弱さ」ではなく「気のバランスの揺れ」として捉えます。
呼吸・経絡・鍼灸・養生を通じて、その人本来のリズムを取り戻す。
言葉にできない感覚やエネルギーを扱える医学だからこそ、進化系人間の“感じる力”を社会に生かすための翻訳の橋渡しができるのです。
鍼灸院の役割
鍼灸院の役割は「治す」ことではなく、その人の感性が社会の中で生きやすくなるように「翻訳」することです。
過敏な神経を「過剰反応」と見なすのではなく「高性能センサー」として尊重する。
エネルギーの揺れを「不安定」と言わず、「調整のサイン」として受け止める。
その人のリズムに合わせて整えることで、
進化した感性が地球上でのびやかに機能できるようになります。
感性の時代へ
これからの時代は、「感じ取る力」が主役になります。
共感・直感・創造、それらはAIにも代替できない、人間の本質的な能力です。
だから今、「感じすぎてしんどい」と思う人たちは、実は時代の最前線に立つ存在。
その生きづらさは、進化の副作用。
東洋医学や心理の役割は、その副作用を抑えるのではなく、調律していくことです。
「できない」ではなく「合わない」
「弱い」ではなく「敏感である」
「壊れた」ではなく「変化に先行している」
それを一人ひとりに伝え、自分への否定をほどき、
「自分らしいリズム」で生きられるように整えていく。
進化とは、最初は孤独に見えるもの。
だからこそ、互いに寄り添いながら、人と人をつないでいくことが大切です。
感じすぎて生きづらいあなたへ
その感性は、これからの時代が必要とする「光のセンサー」です。
どうか、自分を責めず、少しずつその感受の翼をひろげてください。
あなたの存在が、未来の調和をつくっています。
茜メソッド認定養成講座(Lesson1〜6)

プロの為の学校
茜メソッド認定養成講座がLesson 6まで終了しました。
◆ Lesson1
座学 ▶︎ 茜メソッド総論 :茜メソッドとは何か?
⚫︎全ての施術が茜メソッドなので、共感できない場合はLesson1でやめることも可能。
実習 ▶︎ カウンセリング
⚫︎ラポール(信頼関係構築法)を形成し、安心して施術を受けてもらえる関係作り。
実技 ▶︎ 徹底的にプロの姿勢をつくる
⚫︎タオルワーク、楽な立ち位置、信頼感のある所作、安心させる会話術など徹底的にプロの姿勢をつくる。
◆ Lesson2
座学 ▶︎ 茜メソッド理論(身):痛みの種類と痛みが起こる意味を知る
⚫︎痛みを止めるには原因にアプローチできるかが重要。
実習 ▶︎ 脈診、舌診で証をとる方法
⚫︎脈、舌から体内がどういう状態か見極め、大まかな治療の方針を決める。
◆ Lesson3
座学▶茜メソッド理論(身):体質や環境など慢性疾患の原因と問題点を学ぶ
⚫︎慢性化した原因は何か判断し、患者自身の生活習慣や考え方の変化を促す。
実習 ▶︎ 鍼が怖い、痛みが強い人へのアプローチ法
⚫︎痛みの少ない、ゆらぎ法(緩痛鍼)を習得する。
◆ Lesson4
座学 ▶︎ 茜メソッドの理論(身)(心):病院で治りにくい疾患の原因を探る
⚫︎対処療法を続けているだけでは改善はしない。
実習 ▶︎ 病院では治りにくい疾患を改善へ導く
⚫︎めまい・難聴耳鳴り・視力低下・自律神経症、起立性調節障害など。
◆ Lesson5
座学▶茜メソッドの理論(身)(心):原因不明の症状や疾患で苦しんでいる人を救う鍼灸
⚫︎一人一人に寄り添ったアプローチ法
実習▶︎ どうせ治らない、から希望にかえる鍼灸
⚫︎自己免疫疾患・後遺症・異痛症、癌、難病、精神疾患など。
◆ Lesson6
座学 ▶︎茜メソッドの理論(心): 精神疾患と精神症状の種類と原因を学ぶ
⚫︎精神を病む人と身体を病む人は何が違うのか
実習 ▶︎ 鍼灸治療+カウンセリング法で精神症状への改善率を上げる
⚫︎うつ症状・パニック障害・不眠症など。
神戸東洋医療学院にて1日講座【美容鍼灸とメンタルケア】

神戸東洋医療学院で卒業生として講義をさせていただきました。4年目となりました。
年を追うことに女性の鍼灸師志望が増えていることに驚かされます。
少しでも私の経験や想いが役に立てばいいなと思います。
私自身も一年生の最初に習う「整体観念」が鍼灸師として1番大事って事に気づいたのは卒業して何年も経ってからです。
東洋医学の根本にある考え方のひとつが「整体観念(せいたいかんねん)」です。
これは「身体を部分ではなく、全体として みる」という考え方です。
たとえば肩がこるとき、単に「肩の筋肉が固い」とは限りません。
胃腸の疲れや、ストレス、睡眠不足、気温や湿度の影響など、
さまざまな要素が関わり合って「肩こり」という形で現れているのです。
東洋医学では、内臓・筋肉・血流・気のめぐり、そして感情までもがすべてつながったひとつの生命の流れとしてとらえます。
また、人の身体は自然のリズムの中で生かされており、季節の変化や気候、月のリズムなども私たちに影響を与えています。
このように、身体の中だけでなく「自然との調和」までを含めて全体を見る。
それが「整体観念」です。
日々の不調を、“どこかひとつの異常”ではなく、
身体全体と心、そして生活や環境とのバランスの乱れとしてとらえると、原因が見えやすくなり、自然と回復の方向に向かいやすくなります。
東洋医学や鍼灸、茜メソッドの施術も、この「整体観念」をもとにしています。
ひとつの症状を治すだけでなく、心と身体が調和し、自分らしい自然体に戻ること。それこそが「整う」ということなのです。
技術ばかりではなく、ヒトに寄り添える人間性がとても大切な仕事です。
1人でも多くの人を救える鍼灸師になって欲しいです。